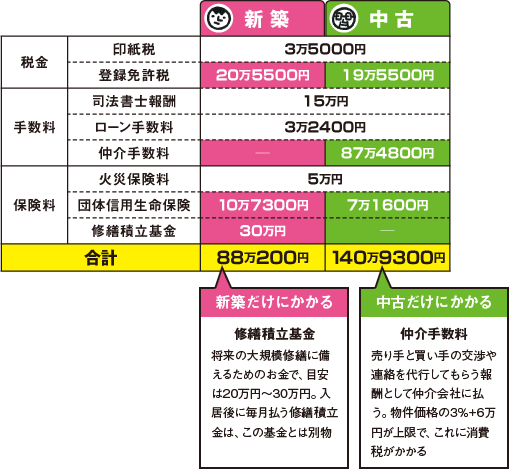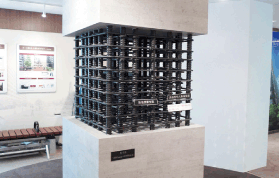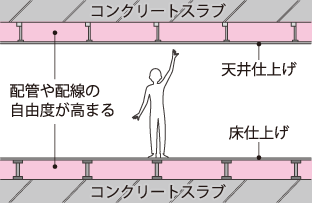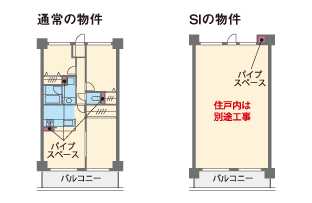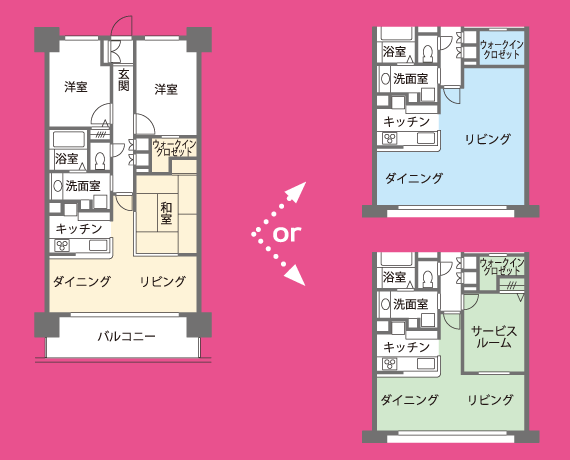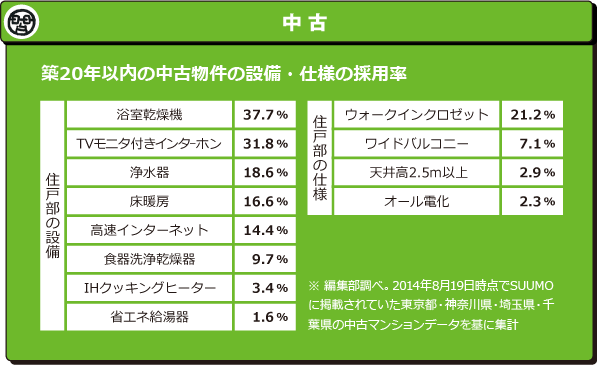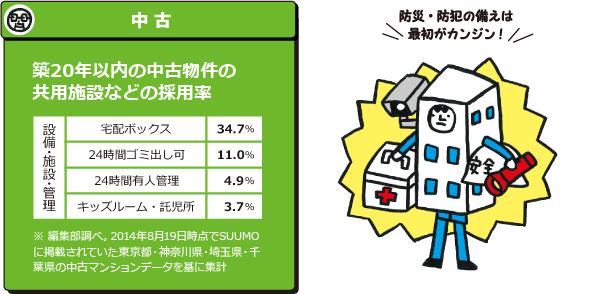2024年05月16日
借地権とは?種類や特徴、メリット・デメリットをわかりやすく紹介
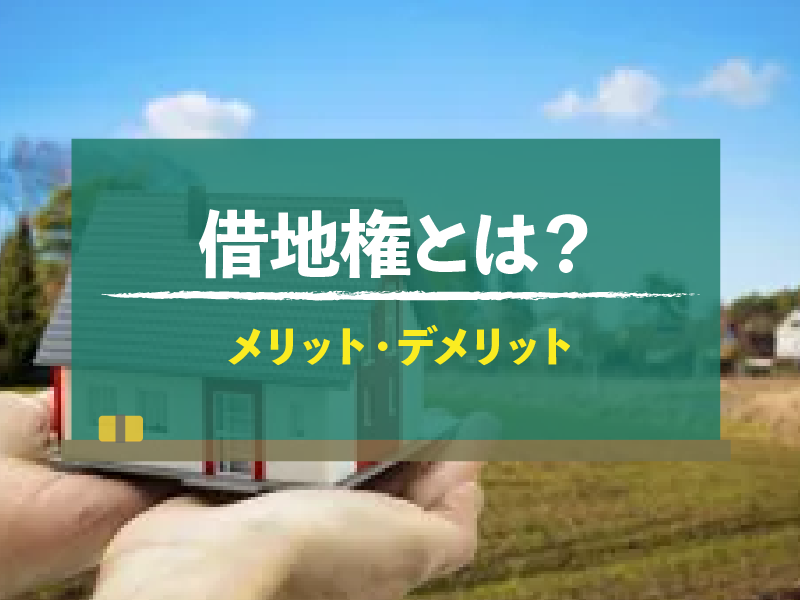
借地権とは、建物を建てるために地代を払って他人から土地を借りる権利のことです。そのため、建物がない駐車場や資材置き場などは含まれません。
借地権には賃借権と地上権の2つがあります。
賃借権の場合は、第三者に建物を売却する時は地主の承諾が必要です。
地上権の場合は自由に売却や転貸することができます。
現在のところ一戸建ての場合、実際に多くあるのは賃借権です。
こちらでは、借地権の土地に建物を所有している方、借地権のマンションや一戸建ての購入を迷っている方に、借地権の種類や特徴、メリット・デメリット、対抗要件についてご紹介します。
1.借地権とは
借地権とは、土地の持ち主から土地を借りる権利のことです。借りた土地に建物を建てた場合、様々な制約があります。借地権の特徴についてご紹介しますので、借地権付きの物件を購入する際の参考にしてください。
1-1.借地権の特徴
借地権の特徴は以下の通りです。
・土地の権利は地主にある
・地主に対して地代を払う
・借地に建てた建物を無断で売却することができない
・建て替えは事前に地主へ連絡する
・契約期間が満了したら更地にして地主に土地を返還する
・土地の持ち主のことを「地主」といいます。地主から借りた土地に建物を建てた場合、建物の権利は借りた側にありますが、土地の権利は地主のものです。
・借地の場合、土地を借りた「借地人」が地主に対して地代を払います。
また、借りた土地に建物を建てた場合、地主の許可なく売却することはできません。建物を建て替える場合は、地主に連絡が必要です。
借地には契約期間があります。契約期間が満了し、契約を更新しない場合であれば、土地を更地にして地主に返却します。
借地権の土地は、買った土地に比べて土地や建物に対する自由度が低くなることが特徴です。
1-2.借地権の契約更新
借地権には契約期限がありますが、更新も可能です。「旧借地法」で土地を借りた場合、地主に正当な理由がない場合、基本的に契約は自動更新されます。
普通借地権など、1992年8月1日以降の「借地借家法」では、契約の存続期間が法律により定められています。普通借地権なら、半永久的に土地を借りることも可能です。
借地権の土地の上に立つマンションや一戸建てを買うときは、借地権の種類に注目することがポイントです。次の章では、それぞれの借地権の種類や特徴を詳しくご紹介します。
2.借地権の種類
大きく分けて2種類あり、借地法(旧法)と1992年8月1日に施行された借地借家法が存在します。旧法は借地人の権利が強く、土地の返還がむずかしいなど地主側に不利な面がありました。新しい借地借家法では、借りられる期間を定めた定期借地権も設けられています。
2-1.借地法(旧法)
1992年(平成4年)8月より前から土地を借りている場合は「借地法」(旧法)が適用されます。
契約期限は決まっているが、更新することにより半永久的に借りることができる。 木造などの場合、存続期間は30年(最低20年)で更新後の期間は20年。鉄骨造・鉄筋コンクリートは60年(最低30年)、更新後の期間は30年となっている。
2-2.借地借家法
1992年(平成4年)8月以降から借り始めた場合「借地借家法」が適用されます。
借地借家法には5つの種類があり、普通借地権と定期借地権が存在します。
旧法と普通借地権の違いは、構造により存続期間が違うことなどです。
| 1.普通借地権 | 契約期限は決まっているが、更新することにより半永久的に借りることが可能。 存続期間は構造に関係なく当初30年、合意の上の更新なら1回目は20年、以降は10年となっている。 |
|---|---|
| 2.定期借地権 (一般定期借地権) | 定期借地権付き一戸建て、定期借地権付きマンションともに住宅用として土地を賃借する。契約期間は50年以上。更新はなく契約終了後は更地にして返還。 |
| 3.事業用定期借地権 | 事業用(店舗や商業施設等)で土地を借りる場合のもの。契約期間は10年以上50年未満(2008年1月1日の法改正以前は10年以上20年以下)。契約終了後は更地にして返還する。 |
| 4.建物譲渡特約付借地権 | 契約から土地所有者が建物を相当の対価で買い取る決まりがある。 契約期間は、30年以上。 |
| 5.一時使用目的の借地権 | 工事の仮設事務所やプレハブ倉庫等で一時的に土地を借りる。 |
上記のような種類となっていますが、現在は(1)旧法に該当するケースが多いようです。借地権付きの家を所有していたり、相続したりする場合は、契約期間を確認しておくといいでしょう。
3.借地権の物件のメリット・デメリット
借地権の特徴は、他人の土地でありながら、半永久的に居住することが可能なことです。しかし、契約の更新や家を手放す時に地主の許可が必要などのデメリットもあります。
借地権の特徴を、メリット・デメリットにわけてご紹介します。
3-1.借地権のメリット
借地権のメリットは以下の通りです。
- 土地の固定資産税、都市計画税の負担がいらない (地代で負担していることにはなる)
- 特に借地法(旧法)の場合、法律に守られており半永久的に借りられる
- 土地が利便性や立地条件の良い場所にあることが多い
- 借地権付きの建物を購入する場合、所有権付きより安く手に入る
住宅を取得していると、土地や建物に固定資産税がかかります。借地権がある土地の建物には、土地に対する固定資産税と都市計画税がかかりません。
そのため、土地も建物も自分で購入した物件よりも税金を安く抑えられることがメリットです。(土地の上に立っている建物には税金がかかります。)
借地権の物件は、主に利便性や、価格の面でメリットがあります。
3-2.借地権のデメリット
借地権の土地に建つ物件のデメリットは以下の通りです。
- 地代の負担がある
- 土地が借主の所有物にはならない
- 更新時には更新料が必要な場合がある
- 建物を売却する際には地主の承諾がいる(譲渡承諾料が必要)
- 増改築の際、地主の承諾がいる(承諾料が必要な場合も)
- 借地権は第三者に売却するのがむずかしい
せっかくマイホームを持っても、自由が少なくなることが借地権のデメリットです。
土地に対する固定資産税や都市計画税がかからない一方で、地代の負担があります。また、どんなに地代を払っても、借りている土地は自分の所有物にはなりません。そのため、建物の売却や家の増築をするときは地主の承諾が必要です。承諾料が必要なケースもあります。
借地権の土地の物件は、所有権の土地の物件に比べ、好条件が揃っていても買い手を探すことが困難です。借地権の物件を売却するときは、デメリットを上回るメリットが必要とされます。
4.借地権の対抗要件とは。地主が土地を売却した場合
地主が土地を第三者に売却した時は、これまでの権利がどうなるのか気になるところです。土地が売却された場合でも、建物があり借地人の登記がされている場合は、新たな所有者に土地を明け渡さなくても済みます。
ただし借地人が父、建物登記は息子などと、名義が違う場合は対抗できませんので注意が必要です。また、登記した建物が火事などで滅失した場合は、滅失から2年間は建物を特定するための必要な事項と、滅失した日、新たな建物を建築する旨を、その土地上に立札等を掲示することで対抗することができます。
また、借地権(底地権)を国が持っているケースも稀にございます。
この場合ですと国から土地を買い受けることも可能です。
お困りごとございましたらY’s upまでご相談ください!







 します。
します。








 不動産営業は、人の人生を左右するほどの大きな資産を扱う仕事です。責任が大きく、やりがいのある仕事ですので、興味がある方はぜひ挑戦してみてください!
不動産営業は、人の人生を左右するほどの大きな資産を扱う仕事です。責任が大きく、やりがいのある仕事ですので、興味がある方はぜひ挑戦してみてください!